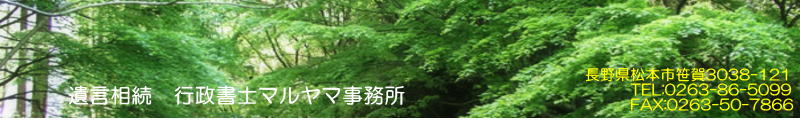
��Аݗ�
 |
����Аݗ��͂���ȂɊȒP |  |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
��Аݗ����ȒP�Ƃ͌����Ă���p�͂ǂ̂��炢������̂ł��傤�B
���{���́u1�~�v�ł��悭�Ȃ�܂������A�芼�̔F��萔���A�o�^�Ƌ��ŁA
���̑��A�ؖ������s�萔���Ȃǂ����v��25���~�قǕK�v�ł��B
���\�|����܂��ˁB
�@�@�@�@�@�����������ł͓d�q�芼�ɂ��邱�ƂŁA�芼�ɓ\��40,000�~��
�@�@�@�@�@�@�@�@������ߖ�ł��܂��B
��Аݗ��Ő悸���߂邱�Ƃ́A
�@�@�@�@�@�@��Ж��E�{�X�Z���E���Ɠ��e�E���{���̊z�E����
�@�@�@�@�@�@���s�\���������E�����̕��@�E���Z���Ȃǂł��B
���{���E�E�E�E�E1�~����ݗ��ł���悤�ɂȂ�܂������A�ΊO�I�M�p�̖ʂ���A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�܂��A���{���͉�Аݗ���Ɏ��R�Ɉ����o���g����̂ŁA
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�^�]������J�Ǝ����͎��{���Ƃ��Ĉꎞ��s�����ɐU�荞�݂܂��傤�B
���Z���E�E�E�E�E�����̕������ƔN�x����3��������12���ƌ��߂܂����A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ŗ��m�ɋL���⌈�Z���ނ̍쐬���˗�����ꍇ�A���Z�Ȏ��������炵��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@8���A10���ł��ǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@����i���v�j���ł��オ�錎������ɁI�I
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������ɏオ�������v��1�N�|���Đߐłł���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������ɏオ�������v��1�N�|���Ď��Ƃɓ����ł���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������ɏオ�������v�Ŕ������Œ莑�Y�̌������p���1�N���i12�������j�v��ł���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����\�z�ɔ����ė��v���o�Ȃ������ꍇ�A1�N�|���Čo��팸���Ԏ�������ł���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@����i���v�j���ł��オ�錎�������ɂ���ƑS�����̏�
�L����А��x���p�~���ꊔ����Ђɓ���
�@���������A�����1���̂悤���L����Г��l�̃V���v���ȉ�Ђ������B
�@����������L����Ђ͓��ʗL����ЂƂ��āA������Ђ̈����ɂȂ�܂��B�܂��A
�@�@�@������������ЂɕύX���ł��܂��B
���{��1�~�Ŋ�����Ђ�ݗ�
�@������܂ʼn�Ђ�ݗ�����ɂ͊�����Ђł͂P�C�O�O�O���~�ȏ�A�L����Ђł�
�@�@�R�O�O���~�ȏ�K�v�ł������A���݂����{���P�~�Ŋ�����Ђ�ݗ��ł��܂��B
�@�@�����͌����Ă��A�Љ�I�M�p�x�܂��^�c�ォ���������x�܂Ƃ܂������z�͕K�v�ł��B
��Бg�D�̃����b�g��
�@���l���Ƃ���Бg�D�̂ق����Љ�I�M�p�������B������s����̎ؓ��A�]����
�@�@�@��W�ɂ��L���ł��B
�@���l���Ƃ̏ꍇ�A�����̐ӔC�͎��Ɨp�̕��݂̂Ȃ炸�A�l�̍��Y�ɂ܂ł����
�@�@�@�����ӔC�ł��B������Ђł́A����͏o���z�����̐ӔC���݂̂ŁA�l��
�@�@�@���Y�ɂ͋y�т܂���B
�@���l���Ƃ͖{�l�̎��S�ŏI�����܂����A��Бg�D�͌p���I�Ȏ��Ɗ������ł��܂��B
���@�I�ɐߐł��悤
�@����\�҂̋����͔�p�Ƃ��Čv��ł���B
�@���������̌J�z�T�������܂��B�Ԏ��������������A���N�x�̍����Ƒ��E����
�@�@�@���Ƃ��ł��A�Œ��V�N�J��z���܂��B���̑��A���ʏ��p�̌v��A���k�L���A�O��
�@�@�@����p�A�ݓ|�������Ȃǂ��v��ł�����͍̂l����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�N�Ƃ��A�E�̂ЂƂ�
�@�����Ƃ���������|�C���g

������肽���̂ł����H�E�E�E�E�E�u�������ƂȂ��������������v�ł́A�������܂��@�@
�@���̎��Ƃɏ�M�Ǝu�͂���܂����H�@
�@���̎��Ƃ͎Љ�K�v�Ƃ��Ă�����̂ł����H�@
�@���̏��i�͌ڋq���]��ł�����̂ł����H�@
�@���̎��Ɓi���i�j�ɂ͓��Ƒ��Ђ��^���ł��Ȃ��Z�[���X�|�C���g������܂����H�@
�悭�����邱�Ƃł����A�i���o�[�������I�����[������ڎw���܂��傤�@
�����ɏ�M������A������Љ���߂Ă���̂ł���A�K���������܂��I�I�@�@
�@���ƃA�C�f�A�i�l�����N���N��������́{��Ԃ̈��S�ł�����́j�@
�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�ڋq�����������i����j�����Ƃ��p�����邱�Ƃ��ł���@�@�@�@�@�@
�@�拭�Ȍo�c���O�������Ɓ@
�@���ՓI�Ȋ�{�I���l�ςƂ��Ĉ�т������̂��A��Ƃ��������W���Ă�����ŕs���ł�
����Ƃ�������@�@���Ƃ���������ɂ͂��Ȃ��Ƃ��Ȃ����Ƃ芪���u�l�v�ł��@
�@�@���������g�̈ӗ~�A�\�́A����
�@�@���l���ɂ��l�b�g���[�N
�@�@���p�[�g�i�[�̐l��
�@�@�N�ƌ��3�N�Ԃ̎��ƖڕW���������藧�Ă�i�ܘ_�A���l�v����܂݂܂��j
�@�@���Ȏ����͑��߂ɁA�ؓ����͋ɗ͏��Ȃ��Ɂi�N�Ƃ��l���������玑����~����j
�@�@���ƌv�揑�����ۂ̕����Ɛ����ŏ����グ�Ă݂܂��傤�B�i���ƌv�揑�͎ؓ��̍ۂ�
�@�@�@�@�@�@���������ɂȂ�܂��j
�@�@�@�y���ƌv�揑�̍����z
�@�@�@�@�@���ƑS�̂̃C���[�W�E�E�E�E�E�N�Ƃ̓��@�A���Ƃ̖ړI�A�����̖ڕW�A�s��̒���
�@�@�@�@�A�̔��v��E�E�E�E�E���鏤�i�E�T�[�r�X�E�Z�p�Ȃǂ̓����A�ڋq�̃j�[�Y�i�̔��Ǝd�����T�v�PH�Łj
�@�@�@�@�B�����v��E�E�E�E�E�ݔ������E�^�]�����ȂǕK�v�Ȏ����Ƃ��̒��B���@(���Ȗ{�͂R�O���`�T�O����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�K�v�j
�@�@�@�@�C���x�v��E�E�E�E�E����\���@�@�q�P���~�Ȑ��~��]���i���H�Ɠ��T�[�r�X�Ɓj
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1�u����̔���~����ʐρi��ʓI���i�̔��Ɓj
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���q�P���E1�u����̔��㍂�E1�ƒ�̏���z�Ȃǂ́A�s��������܂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�͏��H��c�����Œ��ׂ�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���x�v��@�@�J�Ə�������3�N�ڂ܂ł̌����ς̔��㍂�E����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�E�l����Ȃǂ̌o��ƕԍϊz�̎Z�o
�@�@�@�@�D�ԍόv��E�E�E�E�E����\�����A���㌴���A�c�ƌo��Ȃǂ��瓖�����v���Z�o
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������ؓ����ԍϗ\��z�A�ƌv��ȂǏ������x�������Z�o
�@�@�@�@�E���̑��E�E�E�E�E�l�Ɩ@�l�A���F�葱���A�Ŗ������ւ̓͏o
�@�@�@�@�@�@�@�W�������̋��F�E���i����邱�ƂŁA�Ɩ��g��@����グ�@UP�@�I�I
�@�@�ŏ���1�N����ςł����A2�N�ڂɂȂ�ƁE�E�E�E�E�E
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
����{���v�� �i���H�X�����̃|�C���g�j
 �@���V�K�J�ƑO�ɓX�܃f�U�C����\������E�E�E���t�A�����}�`��
�@���V�K�J�ƑO�ɓX�܃f�U�C����\������E�E�E���t�A�����}�`���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�X�^�b�t�A�����ɐ����ł���
�@�@�@���i�E�E�E�E�E�j�ɂȂ鏤�i(����)�A�X�̑傫���A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�X�ܓ��̃��C�A�E�g�i�����I�ȓ����j
�@�@�A�l�ށE�E�E�E�E�]�ƈ��i�z�u�A�l���A���ԁA����j�j�����ċM��(�o�c�ҁj
�@�@�@�B�ꏊ�E�E�E�E�E�œK�ȗ��n�i�������X���V�K�ڋq���l���ł���j�A�X�ܑO�f�U�C��
�@�����H�X�͗ʔ̓X�ƈႢ�A���X�q������ƕK������グ�ɂȂ�(���H���𒍕��j�B
�@�@�@�������A���q���������Ȃ���Γ�x�Ɨ��X���Ȃ��B���s���Ȃ����߂ɂ�
�@�@�@���X���̗l�q���O���番����E�E�E�E���i�A���i�A���͋C���C���[�W�ł���
�@�@�@�����X�O�̋q�̕������C���[�W(���ҁj��������@���A���i�A���S�n�B
�@���q�̕s���Ƃ�
�@�@�@�@�@�ڋq�ԓx�E�E�E�u���q�l�͐_�l�ł��v�ʂ̑Ή��A����ׂ�̃��Y���A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�[���A�A�C�R���^�N�g�͍ł��d�v
�@�@�@�@�@���ԁE�E�E�X�A�����ɓK�����҂����Ԃ�����B�i�ł́A�s���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ł��郉�[�����X�͑҂����Ԃ��������A����́A���H�X�ŐH��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������̂ł͂Ȃ����i"���[����"���ɍs���̂��B�j
�@���|�C���g�́����Ȃ��̌o�c�f�U�C�����������肵�Ă��邱�ƁB���オ�L�тȂ�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ƌ����ĉ��i�������Ȃ��A�q�͖�������Ή��i�ȂNJo���Ă��Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@���]�ƈ��̋��炪�o���Ă���1�l���O.�T�l�{�O,�T�l�ƍl���A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�z�[���A���W�A�~�[�e���֓������B�����āA�P�l���P�D�T�l���̓������ł���悤�ɁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�����n�����ɓK������������l����B�n�搫�A���ԑтɍ��킹�����i�\��
�@�@�@�@�@�@�@�@���d���ꉿ�i���������m�F����B�l����ƍޗ���̃R�X�g�͑傫���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�����X�A�q�̖ڐ��ɗ����A�X�܂̊O���王��B
�@�@�u�X���z�[�������������灨���v������{�����W�q�����v�̌��������X�ܓW�J�v
�����q���g�ɂȂ�܂����ł��傤���H
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���Ə��p
 ���o�c���p�~�����@
���o�c���p�~�����@
�i������Ƃɂ�����o�c�̏��p�̉~�����Ɋւ���@�������Q�O�N�P�O���j
�u�܂���̂��Ƃ�����v�ƍl���Ă͂��܂��H
������Ƃ̌o�c�҂̔N���������i��ł��܂��B������A�M�����S���Ȃ����ꍇ�A���Ƃ��X���[�X�Ɏ��̌o�c�҂Ɉ����p����Ă����܂����H
��p�Җ��ł��ߎ��A�o�c�̃m�E�n�E��m��Ȃ��A�]�ƈ�������̐M�p�������Ȃ����̖�肪�����A�o�c�s�U����|�Y�ȂǂɎ����Ă��܂��܂��B
�@�@�@�i���Ƃ̌�p�҂����Ȃ��E�E�E18���j
�@�@�@�i���̎��Ƃ����̑�ŏI���E�E�E15���j
���Ə��p�ׂ̈ɂ͒����Ԃ̏������K�v�ł��B
�@���o�c���̂��̂̏��p
�@�@�@�@���o�c�m�E�n�E�̏��p�i�Ɩ��m���A�l���A���[�_�[�V�b�v�j
�@�@�@�@���o�c���O�̏��p�i�o�c�ɑ��鉿�l�ρA�ԓx�A�M���j
�@�@�@�@�@�@��p�ҋ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�������ŋ���(�e������ٓ��A�ӔC����n�ʁA���o�c�҂ɂ��w���j
�@�@�@�@�@�@�@�@���O���ŋ���i���ЂŋΖ��A�q��ЁE�֘A��Ђ̌o�c�A�Z�~�i�[���j
�@�������A���Ɨp���Y�̏��p
�@�@�@�@����p�҂ւ̏W�����p�i�◯�����ő���������h�~�A���U�̖h�~�j
�@�@�@�@�������̊m�ہi���Њ��⎖�Ɨp���Y�̔������A�����ł̔[�t�j
�@�@�@�@�@�@�@�@����p�҂ւ̐��O���^�E�⌾
�@�@�@�@�@�@�@�@����Ђ��p�҂������l���甃�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�������l�ɑ����n�����A�����̏��n�����A�c��������������
�@�����Ə��p�Ɛŋ�
�@�@�@�@�������ł̌v�Z
| *�����l���擾���� �@���Y�̍��v���z *�����ی��� *���S�ސE�� |
�| | �푊���l�̍� ������p |
�{ | �����J�n�R�N �ȓ��Ɏ� ���^���Y |
�{ | ���������Z�ې� ���x�̓K�p�� �����^���Y |
�� | �ېʼn��i |
| �ېʼn��i | �| | ��b�T���z �T�O�O�O���~�{�P�O�O�O���~�~�@�葊���l�� |
�� | �ېň�Y���z |
| �����ł̐ŗ��\ | ||
| �@�葊�����ɉ�����擾���z | �ŗ� | �T���z |
| �P�O�O�O���~�ȉ� | �P�O% | �\ |
| �R�O�O�O���~�ȉ� | �P�T% | �T�O���~ |
| �T�O�O�O���~�ȉ� | �Q�O% | �Q�O�O���~ |
| �P���~�ȉ� | �R�O% | �V�O�O���~ |
�������Y�P���~���q��A�EB�Q�l�����iA�F�W�O�O�O���~�A
�@�@B�F�Q�O�O�O���~�j����ꍇ�̑����ł́H
�ېʼn��i�@�P���~�|(�T�O�O�O���{�P�O�O�O���~�~�Q)��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�O�O�O���~
�@�葊�����̎擾���z�@�@�R�O�O�O���~�~�P/�Q���P�T�O�O���~
�P�l���̑����Ŋz1500���~�~15%-50���~���P�V�T���~
�����ł̑��z�@175���~�~2�l��350���~
A�̑����Ŋz�@350�~8000���~/�P���~=�Q�W�O���~�@�@B�̑����Ŋz�@�R�T�O�~�Q�O�O�O���~/�P���~=�V�O���~
�@�������ł̌y���[�u
�@�@�@�@�����ꊔ���ɌW�������ł̂W�O%�[�ŗP�\���x(�����Q�P�N�x�n�݁j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ŁE���^�ł̔[�ŗP�\�̓���̂���܂�
�@�@�@�@���݂Ȃ��z���ېłɊւ������
�@�@�@�@�����K�͑�n���̉ېł̓���(�]���z�̂W�O�������z����܂��j
�@�@�@�@�@�@�@�����莖�Ɨp��n���̓���
�@�@�@�@�@�@�@�����苏�Z�p��n���̓���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i������ƒ��z�[���y�[�W�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�s�����m�}�����}������ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s�����m�@�ێR�K�j
��399-0033�@���쌧���{�s����5858-1
TEL�F(0263)88-5967�@�@FAX�F(0263)88-5968�@�@
e-mail�Fmaruyama@gyosei.or.jp
 �g�є�HP
�g�є�HP